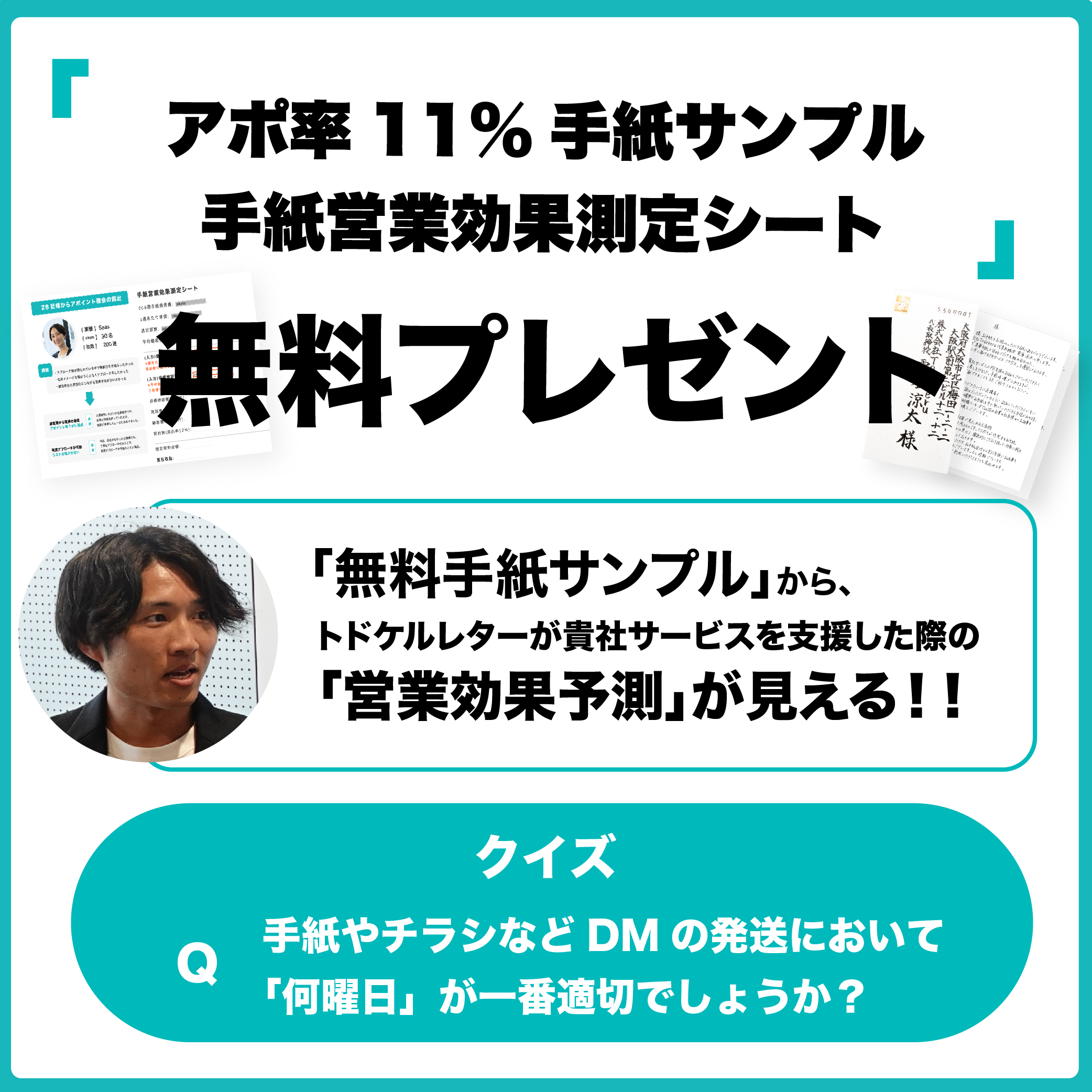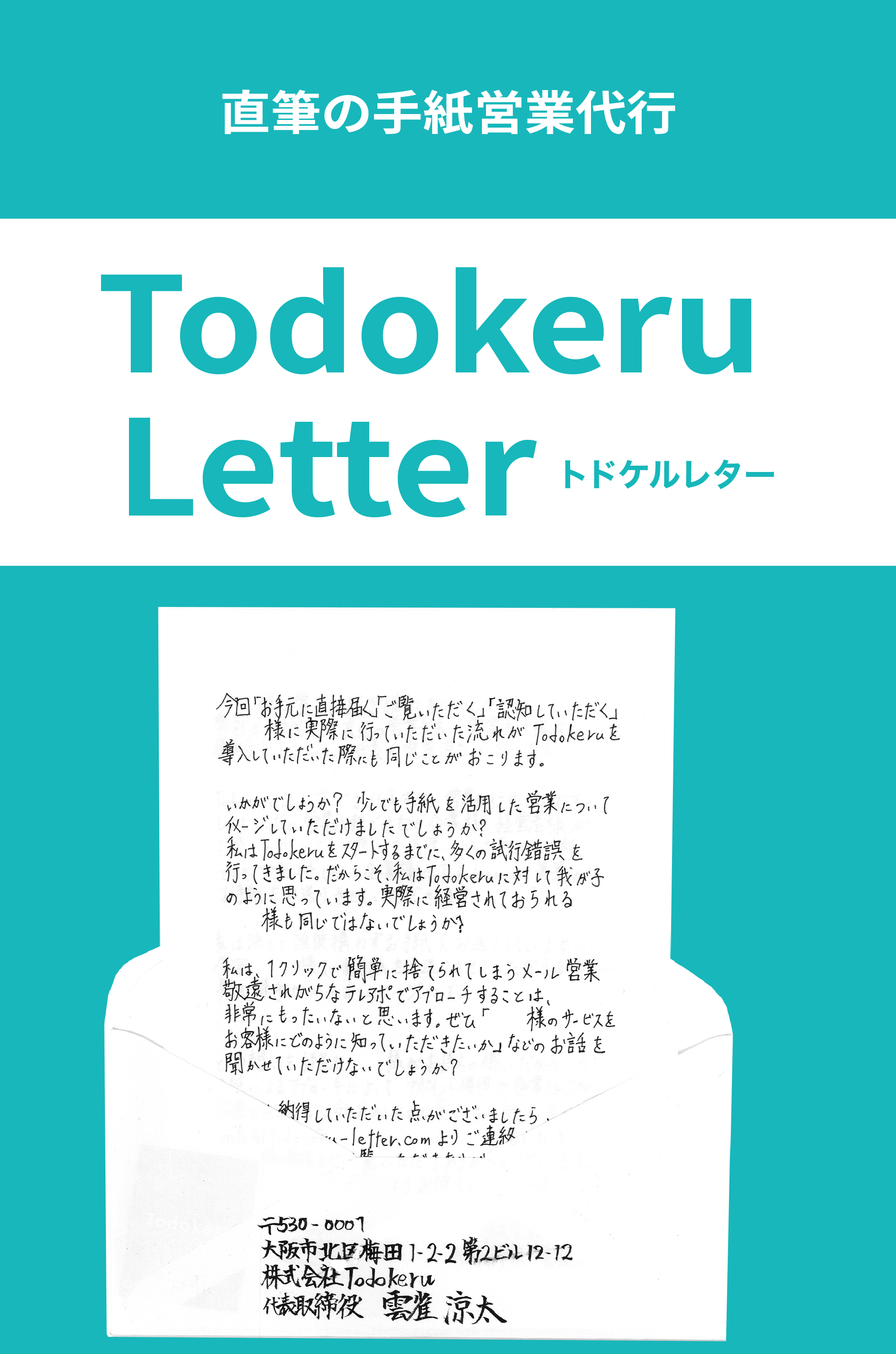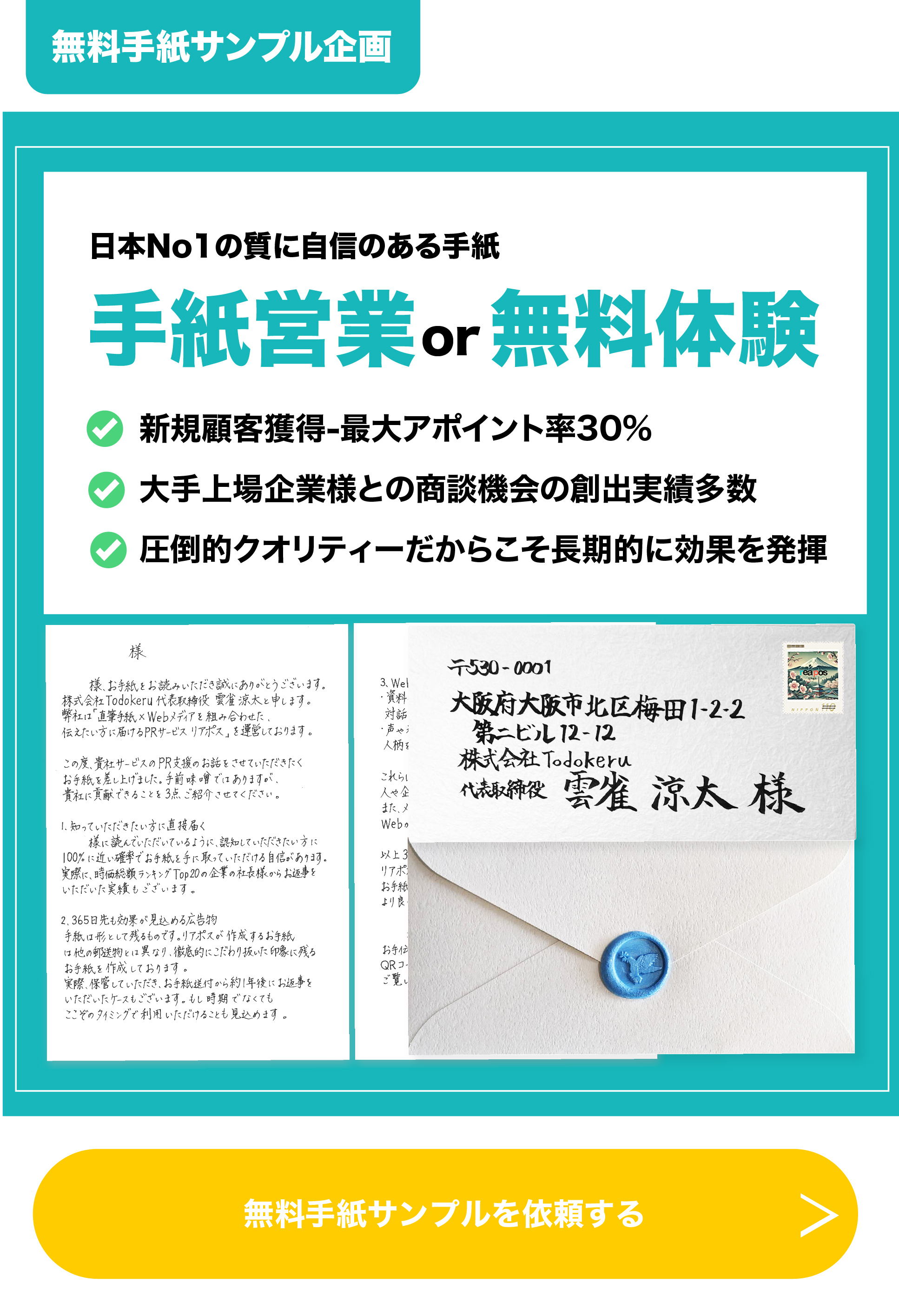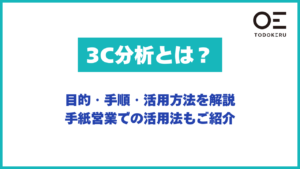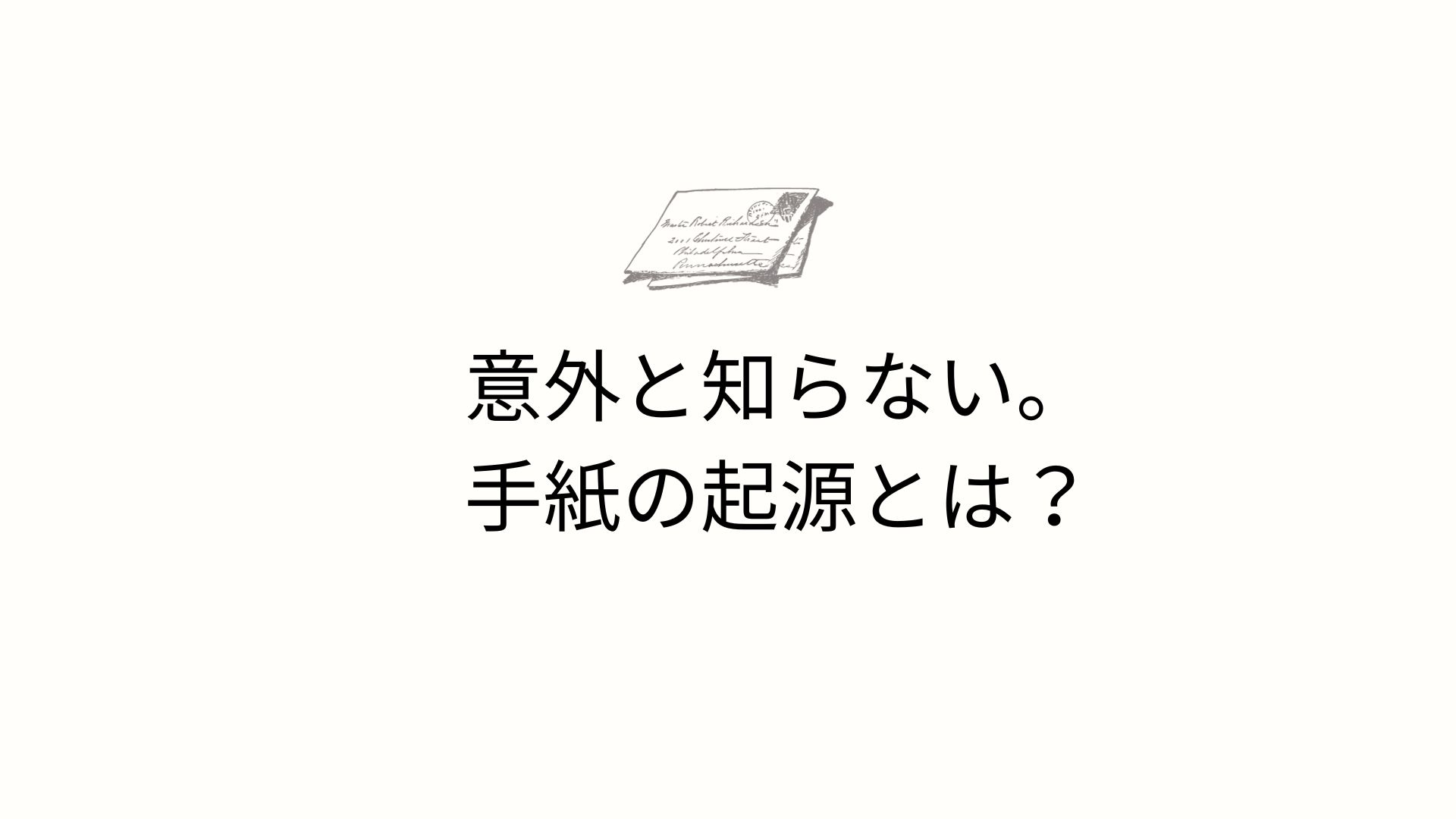
メールや携帯電話で営業や連絡をする人が多くなっている現在。手紙を出す機会は、ほとんどなくなってしまったのではないでしょうか。だからこそ、時に手書きの手紙や葉書を受け取ると、どことなく、その人の人となりが思い浮かび、ふわりと幸せな気持ちになるものです。
日本人にとって手紙とは一体どんな存在なのか?
手紙のルーツは飛鳥時代!
歴史上の手紙といえば、聖徳太子を思い出す人も多いのではないでしょうか?聖徳太子は遣隋使の小野妹子に託した国書に「日出る処の天子、書を日没する処の天子に致す、つつがなきや」と記し、受け取った隋の煬帝が激怒した! というエピソードで有名ですが、本来隋と対等の関係を結びたかったこその言葉でした。
その後、小野妹子が隋に渡る際に託された手紙には、「東の天皇、敬(つつし)みて西の皇帝に白(もう)す」と書き出し、「謹みて白す。具(つぶさ)ならず」と締めてあり、現代の手紙にも使う「敬白」「謹白」といった言葉が飛鳥時代から受け継がれてきていることがわかります。
平安時代に手紙ブーム到来!
平安時代にひらがなが誕生して、女性も日常的に文字を記すようになると、空前の手紙ブームになりました。『源氏物語』や『和泉式部日記』など平安文学の中には、和歌が含まれた文をやりとりするシーンが多々ありますが、そのほとんどは恋文です。
平安時代のラブレターで特に重要だったのが和歌のセンスでした。ダサい和歌など送ろうものなら百年の恋も瞬時に冷めるというもの。想いを伝えるためには教養が問われ、引歌(ひきうた)といって〝入りぬる磯の〟など有名な和歌の一句をつぶやくだけで、本歌(ほんか)の「汐満(しおみ)てば入りぬる磯の草なれや 見らく少なく恋ふらくの多き」を想像し、会話が成立することもありました。
手紙のセンスはどのような紙に書き、結んで届けるかにも見られました。平安時代は、陸奥の国でつくられた陸奥紙(みちのくがみ)と呼ばれる、料紙(りょうし)というかなを書くために加工された紙が貴族に人気だったようです。それを木の小枝に結んで届けるのが一般的で、白い紙の文を梅の花が付いた折枝(おりえだ)に結んだり、青い紙を柳の折枝に結んだり、色の取り合わせにも美意識を宿らせました。
ちなみに、「手紙」という言葉が使われるようになったのは江戸時代のこと。平安時代には「文(ふみ)」や「消息(しょうそく)」と表現されていました。
今も守られている?鎌倉時代に手紙のマナーが制定された!?
手紙がブームになると「書札礼(しょさつれい)」という手紙のマナーも定められていきます。鎌倉時代後期の弘安8(1285)年、亀山上皇が編纂を命じて作成された「弘安礼節(こうあんれいせつ)」は、公家や武家、僧侶などの間で礼式の基本となり、その一部は書札礼の基本として明治維新まで尊重されたようです。
マニュアルに従いながらも、相手にいかに上手に想いを伝えるかは、個人の技量。気持ちを揺さぶる文章と文字で、出世を願ったり、お金を工面したり、反省したり、愛をささやいたり……。はるか昔に書かれた手紙でも、現代に生きる私たちとそう違わない、人間ドラマが見えてきます。
ここまでご覧いただいた方は「手紙」というツールは相手に想いを伝える上で必要不可欠のツールだと思いませんか?スピードが求められる現代。手間のかかる手紙ではありますが、手紙を営業に活用することで、相手に想いが伝わると思いませんか?ぜひ、手紙営業に少しでも興味のある方は下記よりご連絡ください。